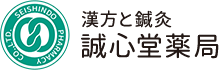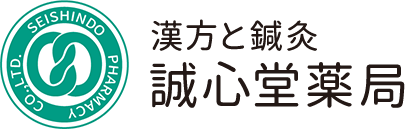腎臓と便秘の関係とは?!
●腎臓病が気になる方が便秘になりやすい理由


-
1. 腎機能低下による影響
腎機能の低下で、たまった老廃物が腸内で善玉菌と悪玉菌のバランスをくずしたり、腸の血流障害・活動量が低下したりすると考えられています。 -
2. 食事制限による影響
腎臓病ではカリウムやリンの制限があるため、野菜や果物を意識的に控えるため、食物繊維が不足しやすくなります。
食物繊維が不足すると、腸の動きが鈍くなり便秘になりやすくなります。 -
3. 水分摂取の制限
腎機能が低下すると、水分の摂りすぎによって、むくみや高血圧を悪化するため、水分摂取を制限することがあります。
しかし、逆に水分が不足すると便が硬くなり、便秘を引き起こしやすくなります。 -
4. 薬の影響
リン吸着薬や鉄剤→便秘を引き起こすことがあります。
利尿剤→体内の水分が減り、便が硬くなることもあります。
-
1. 腎機能低下による影響
腎機能の低下で、たまった老廃物が腸内で善玉菌と悪玉菌のバランスをくずしたり、腸の血流障害・活動量が低下したりすると考えられています。 -
2. 食事制限による影響
腎臓病ではカリウムやリンの制限があるため、野菜や果物を意識的に控えるため、食物繊維が不足しやすくなります。
食物繊維が不足すると、腸の動きが鈍くなり便秘になりやすくなります。 -
3. 水分摂取の制限
腎機能が低下すると、水分の摂りすぎによって、むくみや高血圧を悪化するため、水分摂取を制限することがあります。
しかし、逆に水分が不足すると便が硬くなり、便秘を引き起こしやすくなります。 -
4. 薬の影響
リン吸着薬や鉄剤→便秘を引き起こすことがあります。
利尿剤→体内の水分が減り、便が硬くなることもあります。
●腎機能を高めるために便秘を解消する理由とは?


腎機能が低下して、老廃物を尿で排出できない場合、便を排泄することが重要となります。
ところが、便秘になると腸からの老廃物の排泄が滞り、それを処理する腎臓にさらに負担がかかります。
このように、便秘が腎臓にとって負担になることは、一般的に知られています。
では、その反対に、「便秘を治療することで腎機能にとっていい影響がでるかどうか」については、近年までわかっていませんでした。
2020年、慢性腎臓病のマウスに慢性便秘症改善薬を投与する研究で、「腸内環境が改善するとともにクレアチニン値が改善した」という結果が発表されました。※1
これにより、便秘を解消することで腎機能を高める事ができる可能性が示されました。
●腎臓病が気になる方ができる便秘対策
-
1. 食物繊維を適量摂る
食物繊維が多く含まれているきのこや野菜を積極的に摂りましょう。
G3aまではカリウムの制限がないので、1日350gの野菜を食べましょう。
350gはどのくらいかイメージできますか?
目安としては、生野菜なら両手で一杯、加熱したものなら片手で一杯、毎食食べるのがおすすめです。
小鉢なら5皿分(1皿70g)を意識してみましょう。
●献立例
〇朝食
目玉焼き 納豆 ご飯 お味噌汁 ほうれん草のおひたし
〇昼食
野菜炒め (ニンジン、キャベツ、玉ねぎ) 定食
〇夕食
トマトレタスサラダ カボチャの煮物 鯖の塩焼き ご飯
追加ポイント
◎朝ごはんにほうれん草のおひたしを追加するだけでもOK!!
◎お味噌汁を具沢山にする!
◎加熱してカサを減らす!
70gの野菜は画像の通りです。※2
5種類食べるのが難しければ、量を増やして、2種類にすると取り入れやすいですよ。
G3b以降はカリウムやリンを抑えつつ食物繊維を摂ることが重要です。
以下の食品は比較的カリウムが少なめで食物繊維が豊富です。
• キャベツ(茹でることで約半分のカリウム量になります)
• ごぼう(少量)
• しいたけ30g(84mg)
• まいたけ30g(99mg)
• えのきだたけ30g(102mg)
• ぶなしめじ30g(114mg)
• キャベツ(生)100g(200mg)
• キャベツ(ゆで)100g(92mg)
• 白米に麦を混ぜる(押し麦など)
• こんにゃく
また、カリウムが気になる場合は「茹でこぼし」をすると減らせます。 -
2. 水分を適度に摂る
医師の指示の範囲内で水分補給をしましょう。カフェインのない白湯や麦茶などがおすすめです。 -
3. 適度な運動をする
軽いストレッチや散歩をすると腸の動きが良くなります。
-
1. 食物繊維を適量摂る
食物繊維が多く含まれているきのこや野菜を積極的に摂りましょう。
G3aまではカリウムの制限がないので、1日350gの野菜を食べましょう。
350gはどのくらいかイメージできますか?
目安としては、生野菜なら両手で一杯、加熱したものなら片手で一杯、毎食食べるのがおすすめです。
小鉢なら5皿分(1皿70g)を意識してみましょう。
●献立例
〇朝食
目玉焼き 納豆 ご飯 お味噌汁 ほうれん草のおひたし
〇昼食
野菜炒め (ニンジン、キャベツ、玉ねぎ) 定食
〇夕食
トマトレタスサラダ カボチャの煮物 鯖の塩焼き ご飯
追加ポイント
◎朝ごはんにほうれん草のおひたしを追加するだけでもOK!!
◎お味噌汁を具沢山にする!
◎加熱してカサを減らす!
70gの野菜は画像の通りです。※2
5種類食べるのが難しければ、量を増やして、2種類にすると取り入れやすいですよ。
G3b以降はカリウムやリンを抑えつつ食物繊維を摂ることが重要です。
以下の食品は比較的カリウムが少なめで食物繊維が豊富です。
• キャベツ(茹でることで約半分のカリウム量になります)
• ごぼう(少量)
• しいたけ30g(84mg)
• まいたけ30g(99mg)
• えのきだたけ30g(102mg)
• ぶなしめじ30g(114mg)
• キャベツ(生)100g(200mg)
• キャベツ(ゆで)100g(92mg)
• 白米に麦を混ぜる(押し麦など)
• こんにゃく
また、カリウムが気になる場合は「茹でこぼし」をすると減らせます。 -
2. 水分を適度に摂る
医師の指示の範囲内で水分補給をしましょう。カフェインのない白湯や麦茶などがおすすめです。 -
3. 適度な運動をする
軽いストレッチや散歩をすると腸の動きが良くなります。
※1 Nanto-Hara F,Abe T,et al.,The guanylate cyclase C agonist linaclotide
ameliorates disease:Nephrology Dialysis Transplantation 2020
(https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press_20141217_03web.pdf)
※2 https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/2ibent.html
更新日:2025-03-06