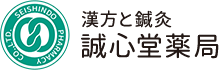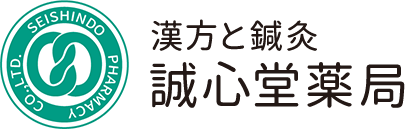腎臓病が気になる方の減塩のコツとは?!
●なぜ減塩が大切なのか?


腎臓病と診断された場合、腎臓病を予防するためには食事管理がとても重要になります。
特に 塩分(ナトリウム)の摂取を控えること は、病状の進行を遅らせるために欠かせません。
塩分を摂りすぎると、血液中のナトリウム濃度が高まり、カラダがそれを薄めようとして血管の中に水分を取り込んで、血液量が増加し血管にかかる圧力が高まり、高血圧となります。
高血圧症の治療では1日当たりの食塩摂取量は3g以上6g未満に抑えることが目標となります。
高血圧になると腎臓の中にある糸球体に圧がかかり、腎機能が低下します。
健康な腎臓であれば、余分なナトリウムを尿として排出できますが、腎臓の機能が低下すると排出が難しくなり、体に水分がたまりやすくなります。
●塩分のとりすぎによる影響


- ・ 高血圧の悪化 → 腎臓の血管が傷つき、さらに機能が低下する
- ・ むくみ(浮腫)の原因に → 余分な水分が体にたまり、手足や顔がむくむ
- ・ 心臓への負担増加 → 体に水分がたまることで 心不全 のリスクが高まる
- ・ 高血圧の悪化 → 腎臓の血管が傷つき、さらに機能が低下する
- ・ むくみ(浮腫)の原因に → 余分な水分が体にたまり、手足や顔がむくむ
- ・ 心臓への負担増加 → 体に水分がたまることで 心不全 のリスクが高まる
●こんなことはないですか?


- ・ハムなどの食肉加工品やかまぼこなどの魚肉加工品をよく食べる
- ・毎食みそ汁やスープを飲む
- ・外食が多い
- ・濃い味付けが好き
- ・醤油やソースをかける頻度が多い
減塩しているつもりでも、いつのまにか過剰摂取していることがあります。
食品にどれくらい塩分が含まれているかは、見た目ではわかりません。
さほど塩辛く感じない食品でも、塩分が意外に多い場合があります。
食肉加工品や魚肉加工品には塩分が多く含まれています。
また、汁物には塩分が多く含まれているので一日一食くらいがおすすめです。
ラーメンやうどんのスープは残すように心がけるだけで、塩分摂取量をカットできます。
●今日からできる!減塩のコツ


-
・しょうゆや味噌は「減塩タイプ」を選ぶ
・塩の代わりにレモンや酢、香辛料(こしょう・唐辛子)を活用
・こんぶ、鰹節、干しえび、などの【だし】やハーブを使って「旨味」を活かす
・香味野菜(しょうが、にんにく、ねぎ、みょうが)など香りのよい素材を使うとその香味が効いて薄味が気にならなくなる
-
・加工食品(ハム・漬物・インスタント食品)を避ける
・野菜は生のままか、茹でた後に和え物にする
-
・麺類のスープは飲み干さない
・味付けの濃いメニュー(丼もの・ラーメン)は控える
・「塩分控えめメニュー」を選ぶ(最近はファミレスやコンビニでも増えている)
-
・野菜やきのこたっぷりの副菜をえらび、ゆっくりよく噛んで食べる(満足度が高まり、食事量と塩分量を控えられる)
・ゆっくり噛んで食べることで、薄味でも満足できる
① 調味料を見直す
② 食材そのものの味を楽しむ
③ 外食や市販食品の塩分に注意
④ ゆっくり食べる
-
・しょうゆや味噌は「減塩タイプ」を選ぶ
・塩の代わりにレモンや酢、香辛料(こしょう・唐辛子)を活用
・こんぶ、鰹節、干しえび、などの【だし】やハーブを使って「旨味」を活かす
・香味野菜(しょうが、にんにく、ねぎ、みょうが)など香りのよい素材を使うとその香味が効いて薄味が気にならなくなる
-
・加工食品(ハム・漬物・インスタント食品)を避ける
・野菜は生のままか、茹でた後に和え物にする
-
・麺類のスープは飲み干さない
・味付けの濃いメニュー(丼もの・ラーメン)は控える
・「塩分控えめメニュー」を選ぶ(最近はファミレスやコンビニでも増えている)
-
・野菜やきのこたっぷりの副菜をえらび、ゆっくりよく噛んで食べる(満足度が高まり、食事量と塩分量を控えられる)
・ゆっくり噛んで食べることで、薄味でも満足できる
① 調味料を見直す
② 食材そのものの味を楽しむ
③ 外食や市販食品の塩分に注意
④ ゆっくり食べる
●減塩して美味しく健康に


腎臓病の食事療法は 制限が多くて大変 と思われがちですが、 工夫次第で美味しく、楽しく食べることができます。
減塩を意識しながら、 腎臓を守る食生活 を続けていきましょう!
【参考】
・日本腎臓学会「慢性腎臓病(CKD)の食事療法」
・厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
更新日:2025-3-13