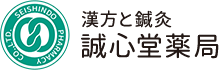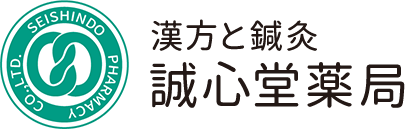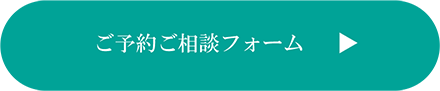体質で考える「無月経」


更新日:2023.5.11
無月経とは?
無月経とは3か月以上月経がない状態を指します。
ただし、妊娠中・授乳中・思春期以前・閉経後に月経がない状態は正常です。
通常月経は、25~38日に一度の周期で訪れ、28±3日が理想的とされています。
無月経には、18歳を過ぎても1度も月経がこない原発性無月経と、前の月経から3か月以上月経がこない続発性無月経とあります。無月経の中では、続発性無月経の頻度が高く、原発性無月経は非常にまれです。
原発性無月経の原因
視床下部性:Kallmann症候群、特発性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症など
下垂体性:ゴナドトロピン放出ホルモン受容体遺伝子変異など
卵巣性:Turner症候群、卵巣発育不全、抗がん剤治療、放射線治療など
子宮性:子宮頸管閉鎖症、子宮奇形など
膣性:処女膜閉鎖症、膣欠損症など
原発性無月経はまれですが、卵巣性が原因となる場合が多いです。
16歳を過ぎても初経が無い場合は婦人科を受診することが望ましいです。
続発性無月経の原因
視床下部性:ダイエットなどによる体重減少・ストレスなどによる性腺機能低下、Chiari-Frommel症候群などの視床下部性高プロラクチン血症など
下垂体性:下垂体腺腫(プロラクチノーマ)による高プロラクチン血症など
卵巣性:早発卵巣不全、手術による卵巣摘出、抗がん剤治療、放射線治療など
子宮性:子宮内膜炎、中絶手術・流産手術・分娩処置などによる子宮内宮癒着など
続発性無月経の原因としては視床下部性が大半です。
無月経の身体への影響
① 無排卵のため不妊の原因となる
② エストロゲン不足のため骨粗鬆症の原因となる
③ プロゲステロン分泌を伴わないエストロゲンの持続分泌のため子宮体癌や子宮内膜癌の原因となる
④ 男性ホルモン過剰のため多毛やニキビの原因となる
妊娠を希望しない場合でも、骨粗鬆症、子宮体癌、子宮内膜癌、多毛、ニキビなどの予防のために治療が必要とされます。
無月経の西洋医学的治療方法
第1度無月経
女性ホルモンのうち、エストロゲンの分泌はあるが、プロゲステロンの分泌が足りない無月経です。妊娠希望がない場合はプロゲステロンの補充により月経を促します。妊娠希望がある場合はクロミッドなどの排卵誘発剤を使用して排卵が起こるように治療を行います。月経流出路閉塞などの器質性無月経の場合は手術を行います。
第2度無月経
女性ホルモンのうち、エストロゲンとプロゲステロン両方の分泌が足りない無月経です。妊娠希望がない場合はエストロゲンとプロゲステロンの補充により月経を促します。妊娠希望がある場合はHMGやHCGなどの性腺刺激ホルモンの注射を使用して排卵が起こるように治療を行います。ただし、体重減少による無月経の場合、標準体重の90%を目指した食事指導や生活指導、カウンセリングなど行い、安易に月経を促さないようにし、少なくとも標準体重の70%を超えてから月経を促す治療を行うことが基本となります。
漢方で考える無月経の治療方法
一つ目に、月経は「腎」と深い関わり合いがあります。
中医学では女性は7の倍数を節目として身体に変化が訪れると考えます。例えば、14歳で初潮を迎え、28歳で成熟し、49歳で閉経を迎えるといった変化です。その年齢による身体の変化は、五臓六腑のうちの「腎」と深い関わりがあります。「腎」は生命エネルギーの根源である「精」を貯蔵し、成長・発育・老化を司り、ホルモン分泌に影響を与えています。この「腎精」が不足すると無月経を引き起こします。
二つ目に、月経は「血」と深い関わり合いがあります。
中医学では、「血」は全身を栄養し、精神活動を支えるものと考えます。「血」の量の不足や、流れの停滞があると無月経を引き起こします。
また、「血」の量の不足や、流れの停滞には、「気」「津液」の流れや過不足も影響を与えています。
「気」はエネルギーであり、「血」を生み出したり、動かしたりするものです。
「津液」は血液以外の体液であり、身体を潤すもので、「血」の原料にもなります。
これらのどこに原因があるかを見極めて漢方や鍼灸の治療を行います。
①精の不足体質
<<腎精不足>>
身体の状態:生まれつきの虚弱体質、飲食の偏りや栄養不足、過労、慢性病、老化、性生活の過多、自慰行為の過多などによって、腎に貯蔵されている生命エネルギーの根源である精が不足している状態です。
治療方法:不足している腎の精を補う「補腎填精」の治療を行います。
|
漢方 |
六味地黄丸、八味地黄丸、亀鹿二仙丸、鹿茸、海馬、紫河車など |
|
ツボ |
太谿、腎兪、関元など |
②気と血の不足体質
<<気血両虚>>
身体の状態:生まれつきの虚弱体質、飲食の偏りや栄養不足、胃腸虚弱、過労、出血性の病気、慢性病などにより、気と血が不足している状態です。
治療方法:不足している気と血を補う「補気補血」の治療をします。
|
漢方 |
十全大補湯、六君子湯、補中益気湯、芍薬、熟地黄、人参など |
|
ツボ |
三陰交、足三里、気海など |
③気と血の滞り体質
<<気滞血瘀>>
身体の状態:精神的緊張やストレス、プレッシャー、食べすぎ、飲みすぎなどにより、気の巡りが停滞しています。気の血を動かす作用は低下し、血の巡りも滞っている状態です。
治療方法:滞っている気と血の巡りを改善する「理気活血」の治療を行います。
|
漢方 |
血府逐瘀湯、芎帰調血飲、香附子、莪朮、三棱など |
|
ツボ |
太谿、内関など |
④津液の滞り体質
<<痰湿瘀阻>>
身体の状態:胃腸機能の低下・食生活の乱れによる胃腸への負荷などにより、余分な水分や老廃物が体内に停滞し、血の巡りが滞っている状態です。
治療方法:胃腸機能を回復し、余分な水分や老廃物の排出を高め、血の巡りを改善する「化痰徐湿活血」の治療を行います。
|
漢方 |
桂枝茯苓丸加薏苡仁、二陳湯、六君子湯、益母草、蒼朮など |
|
ツボ |
豊隆、陰陵泉など |
⑤津液の不足体質
<<陰虚陽亢>>
身体の状態:長期間の精神的緊張・ストレス・プレッシャー、慢性的な睡眠不足、過労、老化などにより津液が不足し、潤いが足りないために熱症状が加わっている状態です。
治療方法:不足している津液を補い、相対的に過剰になっている熱を取り除く、「滋陰潜陽」の治療を行います。
|
漢方 |
枸菊地黄丸、知柏地黄丸、釣藤鈎、天麻、麦門冬など |
|
ツボ |
照海、復溜、太谿など |
生活養生
・睡眠時間は7時間を目安に、早寝早起きを心掛けましょう。
・体重が適正かどうか確認しましょう。BMI(体重kg÷身長m÷身長m)が18.5を下回っている場合、無月経を引き起こしやすくなります。
・偏った食事をしていないか見直しましょう。食事を3食とり、炭水化物・タンパク質・野菜・果物類をバランスよく食べるようにし、甘いものや脂っこいものは避けましょう。
・入浴、映画鑑賞、読書、旅行、レジャーなど、自分に適した方法でストレスを発散しましょう。
無月経でお悩みの方へ
漢方薬の服用や鍼灸の治療では、自分の体質をきちんと確認しましょう。同じ無月経のお悩みの方でもタイプが異なれば、適した治療方法や治療方針が異なります。自分に合った漢方薬や鍼灸治療を選択するために、まずは専門家にしっかり相談しましょう。
実際の漢方相談、鍼灸治療では、チェックにあるような自覚症状だけではなく、舌や脈といった客観的な情報なども考慮して、総合的に体質を確認していきます。体質や治療方針について納得してから治療を始められます。一人で悩まずに、ぜひご相談下さい。
日本全国よりご相談を頂いております。
|

監修 杉本 雅樹
医師
医療法人社団 マザー・キー 理事長
筑波大学医学群卒
筑波大学附属病院などの勤務を経て、平成17年9月、千葉県館山市にファミール産院を開院
現在は千葉県内にて複数の産婦人科診療所を運営

監修 井上桜
薬剤師
国際中医師認定A級(現国際中医専門員)
北里大学薬学部製薬学科卒

監修 上原 康嗣
鍼灸師・誠心堂式三焦調整法認定鍼灸師
琉球大学医学部保健学科卒業
早稲田医療福祉専門学校鍼灸科卒業
早稲田医療専門学校鍼灸科卒業後は整形外科に勤務を経て2005年誠心堂薬局入社
西葛西院長、新浦安店、妙典店院長、行徳接骨院院長を経て、現在は船橋店で院長を務める